
こんにちは!
高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
進学塾リードアップのHPはこちら
- 「社会の勉強の仕方がわからない…」
- 「社会は覚えるだけっていうけど、おもしろくもないし全然覚えられない…」
こんな悩みを抱えている中学生・保護者の方のために、この記事では「社会のテストで”今すぐ”90点取れるようになるための勉強方法」を解説します。
社会は誰でも短期間で大きく成績を上げやすい教科なので、ぜひこの記事に書いてあることを実践して、社会を得意教科にしてください!
社会で高得点を取るために必要なこと
社会は勉強が苦手な子にとっても、5教科の中で最も成績を上げやすい教科です。
なぜなら、「知っているかどうか?」を問う問題がほとんどだからです。
つまり、「暗記」してしまえば、得点を取ることができます。
反対に「暗記」をしていないと手も足も出せず、点数が取れない教科です。
やっぱり社会は暗記の教科
社会はこんな問題が出題されます。
記述問題でも同様です。
記述問題でも、「複数の語句の知識」あるいは「事柄の知識」があるかどうか?が問題になります。
社会では「考えればわかる問題」や「意見を書かせる問題(作文)」は出題されないため、“知識”を試される暗記の教科であることがわかります。
効率よく覚えられる社会の勉強の仕方
「社会は覚えることが重要」というのはわかりました。
それでは「どうやって覚えればいいのか?」が問題になります。
ここからは「効率よく覚えられる社会の勉強の仕方」を解説していきます。
高得点を取るために必要な教材
社会で高得点を取るための知識を覚えるには「学校のワーク」が最適な教材です。
定期テストも「学校ワーク」からそのまま出題される問題がたくさんあります。
もし学校からワークが配布されていない場合は、「教科書準拠ワーク」を用意してください。
“自己流で頑張る”よりも確実に効率の良い勉強ができます。
1300円で購入できるので、「買って損した…」ということは100%ないと思います。
東京書籍:新しい社会
教育出版:中学校社会
帝国書院:中学生の地歴公
日本文教出版:中学社会
その他の社会のおすすめ教材は「社会のレベル別おすすめ問題集23選」の記事で紹介しているので、ぜひのぞいてみて下さい。
重要語句を覚える
まずは重要語句を覚えていきましょう。
重要語句とは、ワークの「一問一答問題」「確認問題」「練習問題」などで出題されているものすべてを指します。
テストや入試で頻出だから問題になっているので、ここは必ず覚えなければいけません。
細かい取り組み方を説明していきます。
即答できるようにする
まずは問題を見てすぐに“即答”できる状態にしましょう。
ここでは書かなくて大丈夫です。
ワークを開いて、“隣に答えを開いて置きながら”問題をやっていってください。
答えがわからない場合は、すぐに答えを見て確認します。
「そうなんだ〜」と確認しながら進めていけばOKです。
この調子で1〜2ページ進めましょう。
7割ぐらい即答できるようになるまで、何度も繰り返し確認してください。
書けるようにする
1〜2ページやり、7割ぐらい答えられるようになったらワークに書けるかテストしていきましょう。
書けなかった問題、間違えた問題については赤で訂正し、以下の要領で問題にチェックを入れてください。
こまめに復習する
あとはテストまで毎日復習して、「△」「×」を「○」にするのみです。
人の脳は何度も繰り返しみたものを重要なものと認識し、記憶することができます。
なので、テスト当日まで永続的に復習をしてください。
「即答できるか復習」なら、10分あればどんどん復習できます。
「時間をかけて丁寧に」より「こまめに何度も」を心がけて復習しましょう。
「確認問題」「練習問題」をマスターできれば70〜80点は取れます。
「まずは70点ぐらいを目指したい!」という方は、ここまでを完璧にしてください。
続いて記述問題や資料・グラフの読み取り問題へいきます。
記述・資料の読み取り問題へ
一問一答や練習問題がバッチリできれば、基礎知識がついている状態なので記述問題を覚える際にも負担が少なく済みます。
記述問題や資料・グラフの読み取り問題はワークなどには「テスト対策問題」や「記述問題にチャレンジ」など、各単元末に設定されています。
記述・資料問題も、「2.1 重要語句を覚える」とまったく同じ手順で覚えていきましょう。
- 繰り返しやる
- こまめに復習する
を心がけてください。
やってはいけない2つのNG行動
テスト勉強をする際に、やってはいけないことが2つあります。
それは
- ワークをやるときに「調べ学習」をしてしまう
- 「まとめノート」を作る
この2つです。
まじめな生徒ほどよくやってしまう傾向があります。
「やってはいけない」というのは、「非効率なのでやらないほうがいい」という意味です。
ワークをやるときに「調べ学習」をしてしまう
まず1つ目の「ワークをやるときに『調べ学習』をしてしまう」とは、「ワークの問題の答えを教科書から探し出して埋めていく勉強法」です。
これはわりと多くの生徒がやってしまっている勉強方法です。
「即答できるようにする」でも説明した通り、“隣に答えを開いて置きながら”問題をやっていってください。
一生懸命探して答えを見つけても「見つける快感」は得られますが、ただの調べ学習になってしまい、記憶には定着しません。
「まとめノート」は作ってはいけない
またノートにテスト範囲をキレイにまとめる人もいますが、これもNG行動の一つです。
まとめであれば授業のノートがあるはずですし、教科書ワークにもとてもよくできているまとめページがあります。
また教科書自体がストーリー付きのまとまったものです。
「まとめ」を見たいのであれば教科書ワークのようなすでにまとまったものを活用するのが良いでしょう。
90点を取るための「地理・歴史・公民」分野ごとのポイント
ここからは、地理・歴史・公民の分野ごとの、90点以上のハイスコアを取るための覚えるべきポイントをお伝えします。
地理の勉強のポイント
地理はグラフや表を使った問題が出題されます。
重要なグラフや表というのが以下のものです。
このあたりが入試でも頻出の重要事項になります。
金額や数字は覚える必要はありません。
『特徴』を覚えておくことが重要です。
教科書を見直したり、ワークにこのような問題が出てきたときにはおさえておきましょう。
歴史の勉強のポイント
歴史は「2.3 記述問題」の通り、記述問題を覚えておくことが重要です。
記述問題ができるようになると得られるメリットもあります。
それは「時代背景」や「重要語句と重要語句のつながり」を理解していくこともできることです。
「資料の問題」は、「その資料が何の出来事と関わりがあるものか」を覚えていきましょう。
「資料の問題」は、『その資料が何の出来事と関わりがあるものか』を覚えていきましょう。
教科書には資料が豊富に載っているので、教科書を見返して出来事と資料を頭の中で結びつけていきましょう。
年号(出来事の順番)を覚えることも大切です。
歴史の問題では「起こった順に並び替えよ」という問題が出題されます。
この問題に対応できるよう語呂合わせなどを使って年号を覚えていきましょう。
公民の勉強のポイント
公民の記述問題では
がよく出題されます。
記述の問題に取り組んでいるときに以上の2点のような問題が出題されていたら必ず覚えておくようにしましょう。
これで社会は90点確定!社会の勉強法まとめ
さいごにもう一度、社会の勉強方法の手順をまとめておきます。
「覚えるのが苦手」という人も、こまめに復習を積み重ねていけば必ず覚えることができます。
社会は誰でも短期間で大きく点数を伸ばすことができ、誰でも“得意教科”にすることができます。
社会の問題集選びで迷っている方は、『社会おすすめ問題集23選』の記事でおすすめ問題集を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ぜひこの記事に書いてあることを実践して、社会を“得意教科”にしてください!!

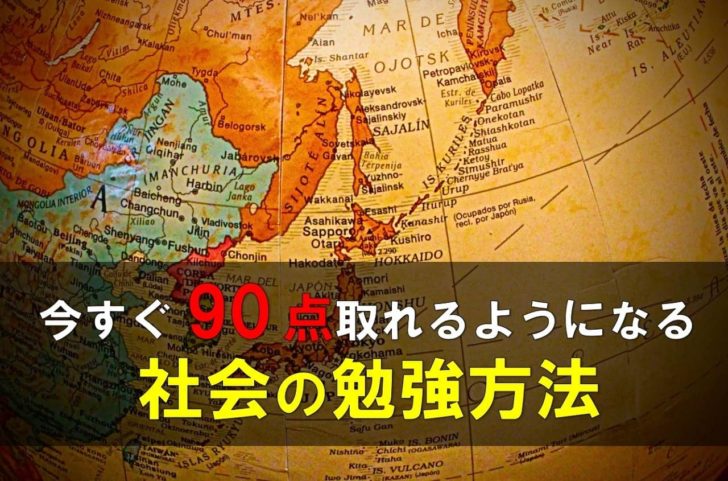












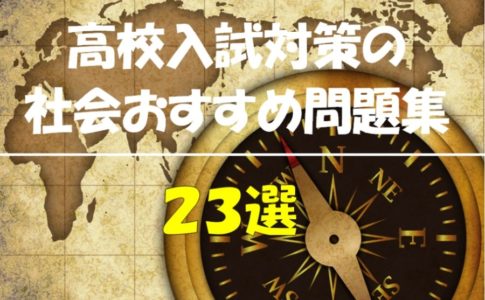
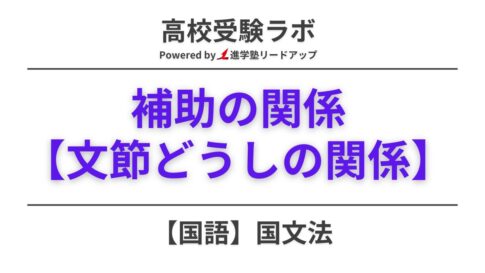
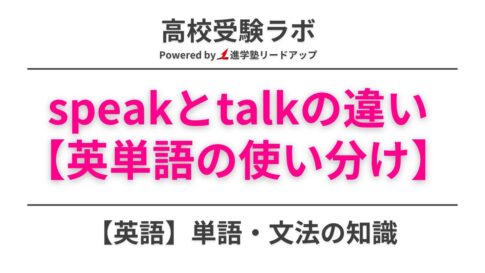











私も今まではノートまとめを中心的にやっていましたが、結局全然頭に入らず、悲惨なテスト結果になってしまいました….(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
ノートまとめをして良いと思ってたのは、「綺麗な字で色ペンで工夫した」
というだけで、ただ自分への満足感だけだったんだと思います…
考えてみれば、テストのほとんどはワークや教科書から出されるもの。頭の良い塾の先生も、そうおっしゃっていました!
これからはワークを繰り返し解き、何度も同じ問題をやっていこうと思います!
答えを見てでも、分からなかった問題はなるべく解けるように頑張ります‼︎
くるねこさん
良い意気込みですね!!!頑張ってください^ ^
とても参考になります。
これを元に後半頑張ってもらいましょう
最初の方にある「覚えるだけっていうけどおもしろくないし覚えられない…」の所の「おもしろくない」はどのように解決すればいいでしょうか。
社会を勉強する意味などが見当たらないので、全くやる気が出ません。社会に興味を持つ方法などを教えてください。
ひくるんさん
興味を持つ方法は、そのことをよく知ることです。
つまり、とりあえず勉強して高得点を取ることです。
人間は知らないことに対して興味は持てません。そういう風にできています。
もちろん、元から理科とか社会に興味を持っている人もいるにはいますが、基本的にそうではない人の方が圧倒的に多数派です。
私自身もそうです。
社会に限らず、全教科に対して、好きでも嫌いでも、なんでもありません(笑)
勉強した結果、点が取れるようになるっていうこと自体は、ぼちぼち楽しいとは思いますが。
「鍛えた結果、強くなる!」というのはゲームと同じなので、ぼちぼち楽しいです。
「興味がある」→「勉強する」ではなく、「勉強する」→「そのことについてよく知る」→「少しぐらい興味が湧く(可能性がある)」
という感じです。
というわけで、とりあえず勉強しましょう!興味は後付けです!
うわ、すごい気になってた事が知れてよかったです。ありがとうございます。
親に、「ノートを作りなさい。」と何回も言われていて困っていました。この記事を読んだので、ここから頑張っていこうと思います。
ぴーちょんさん
コメントありがとうございます♪管理人の山田です。
ノートを作るとしたら、しっかり勉強した後に、過去問や模試などでわからなかったものをまとめる程度で大丈夫ですよ!
頑張ってくださいね♪
ありがとうございます
とても参考になりました。
愛知県88歳さん
嬉しいコメントありがとうございます♪とても励みになります!
わたしもどうやって勉強すればいいのかわからなかったけどこれを見て分かりました‼️ありがとうございました❗
ありにゃんさん
コメントありがとうございます♪
勉強の助けになってよかったです!頑張ってくださいね^ ^
何をすればいいのかわからなかったけどこれを見て分かりました‼️ありがとうございました❗
自分はノートまとめをしていたのですが、書きなぐりでまとめていて非効率ではあったが80後半はとれていました
学校のワークを少ししっかりやってみると90に乗りました!
このサイトを見つけて良かったです
社会特に歴史がほぼ覚えていない状態の中学2年生です。高校受験では来年の秋にある模試の時だけ、平均点ぐらいの点がとれればいいと思っています。
この場合でも教科書ワークをやった方がいいのでしょうか?そのあとは何をすればいいのでしょうか?
教えて頂きますか?
tomoさん
コメントありがとうございます♪高校受験ラボ管理人の山田です。
2年生のうちから受験を意識できているのはすごいことです。大変すばらしいですね!
ご相談に対しての回答ですが,まず社会の受験勉強は,中3の夏休み(7月中旬)から始めれば良いと思いますよ!
中3の1学期まではその時々の定期テストの勉強をちゃんと取り組んでいけばいいです。
受験勉強での参考書は,教科書ワークでもいいのですが,受験用の3年間分が1冊になっているものの方が良いです。
「何をやればいいか?」は,「一問一答」系の問題集1冊と,「受験生の50%以上が解ける 落とせない入試問題 社会」あたりをやるのが良いでしょう。
具体的な参考書は,このサイトの「高校受験社会で9割取るためのレベル別おすすめ問題集23選」の記事でも解説しているので,ぜひ参考にしてください。
勉強頑張ってくださいね♪
質問です!3年間分の内容がまとめてある問題集を3周くらいやったのですが、80行くか行かないかくらいしか取れません。もう少し上げたいのですが、何か方法はありますか?
スズさん
コメントいただきありがとうございます^ ^
80点は素晴らしいですね!80点とれているということは、おおまかな基礎知識は頭に入っていると思います。あとは『抜けている部分(知識の穴)』を埋めていく作業になります。
何をやればいいか?ですが、「全国高校入試問題正解」を解きまくるのがいいです。これを解いていき、間違えた問題、分からなかった問題、合ってはいたが曖昧なまま答えてたまたま合っていた問題、これらをすべてノートにまとめていきます。そのノートには、自分の『知識の穴』だけが書かれたノートになるので、それを復習やすき間時間に読書して、覚え込みを行い知識の穴を埋めていきます。
この作業をきちんとやりながら20~30県分解いていけば、どんな問題がきても確実に90点取れる状態になれます!ぜひやってみてください^ ^
ありがとうございます!
やってみます!
私はいつもまとめのようなものを作り、重要なところをオレンジで書いて赤シートでかくして暗記をしています。やはりこの勉強方も非効率なんでしょうか?
ゆんさん
コメントいただきありがとうございます^ ^
結論を言うと、得点が取れていれば全く問題ないです!
補足を付け加えますと、まとめノートをつくること自体が良くないというより、テスト勉強やり始めの「まだ何も覚えていない状態」でいきなりまとめノートをつくると非効率となることが多いです。
「ワークなどで問題をやる」→「ある程度覚える(今回の勉強の全体像を把握する)」→「(全体像を把握したうえで)まとめノートをつくる」の順番のほうが効率が良いですね!
中2です。
毎回、ワークを4.5回やっても、20点から30点しかとれず、どうしていいかわかりません。時間もかけ、覚えたつもりでいるだけで、やはり覚えていないだけでしょうか?
期末は平均点はとりたいです。どのようにやり方を変えればとれますか?
てらさん
コメントありがとうございます^ ^
自分の感覚的に『しっかり覚えられている』のか『正直あやふや、覚えられていない』どちらでしょうか?
「ワークを4,5回やる」というやり方は合っていますよ!2回目以降は「ちゃんと覚えられているかテストしながらやっていく」必要があるので、そこで覚えられているか(覚えたつもりになってしまっているだけか)をはっきり区別していきます。
それを繰り返していって、「すべて完璧に覚えた」状態になるまでに、結局4~5回かかるというイメージです。
がんばってくださいね!
明日試験なんですがー、
いつもは90前半くらいありますが
今回は難しいので行かないかもしれません
中々二官八省が覚えられません….
質問失礼します!
私は、中三で受験生なのですが 社会科もそうですが暗記全般が苦手です。。(理科や国語の漢字など)
ワークなど何回もやり、親にも協力してもらいテストなどもしてほぼ完璧な状態で学校のテストに挑んだのですが、私が本番に弱いタイプなのか頭が真っ白になり焦ってしまい40点くらいしか取れませんでした…。
どのような勉強を他にすれば最後まで暗記出来るのか、そしてテスト(本番、受験など)に強くなれるのか教えて欲しいです。
よろしくお願いしますm(*_ _)m
ねこさん
コメントいただきありがとうございます♪
結論を言うと、暗記は何回も繰り返し+覚えているかチェック(=テスト)を行うしかありません。
実際ねこさんも『ワークなど何回もやり、親にも協力してもらいテストなどもしてほぼ完璧な状態で』とありますので、それで間違いないと思います。
しかし、厳しいことを言ってしまいますが、頭が真っ白になったということは完璧ではなかったのだと思います。
極端な例かもしれませんが、たとえどんなに緊張状態でも、自分の名前や普段会う友だちの名前をど忘れしてしまうことはないじゃないですか?
なぜかというと、毎日あるいはしょっちゅう会う(=めっちゃ反復してる)から、完璧に覚えてる(というか自分の中のアタリマエになる)わけです。
極論これと同じですので、アタリマエになるまで繰り返して覚えるしかありません。
本番に強いとか弱いとかという概念もなくなります。
ということで、何度も繰り返しチェック&テストを行い『完璧』にしましょう!
覚えて、時間がたつと忘れる どうすればよいでしょう?
時間が経つと忘れるのは、当然のことです!
忘れてしまうことからは逃れられません。
ですので、入試まで勉強し続けて知識のメンテナンスをする必要があります。
どんなに少なくても、月に1回は総復習というか、その知識に触れないとダメです。忘れてしまうので。
コメント失礼します。
私は、最近教科書に緑ペンで線を引いて、赤シートで隠して、教科書をほぼ覚えた状態にしてからワークを解く、という勉強法をしていたのですが、最近70点台ばかりになってしまいます。
この勉強法はやっぱり効率が悪いんですかね?
教科書よりも、ワークを重要視した方がいいのでしょうか…?
あいすさん
こんにちは、山田です。
コメントいただきありがとうございます!
そうですねー…それも悪くないと思いますよ。
重要語句とかは確実に覚えられると思いますし(見ただけで漢字もちゃんと覚えられるならです)。
ただ、定期テストはあくまでワークなどから出題されるので、ワークの問題もすべて完璧にする必要がありますね!
そうしたら、まあ悪くても85点は切らないです!
あいすさんのやり方(教科書→ワーク)も悪いとはまったく思いませんが、個人的なおすすめは「ワーク→教科書で細かいところを詰める」の順ですね。
参考になれば幸いです^ ^
中3の受験生です。全科目成績はよくないんですが、中でも社会が10から20点台をさまよっています。テスト前には自分なりに一生懸命勉強してるつもりが結果は毎回同じ…。最近ではどうしても社会の苦手意識から勉強を避けてしまっています。
苦手意識をなくすにはどうしたらいいですか?また勉強方法もよくわからなくなっています。
だるだるさん
こんにちは、山田です。
コメントいただきありがとうございます。
10~20点をさまよっているということは、重要語句が覚えられていないと思います。
勉強方法のやり方も含めて、それはこのページの内容を参考にしてもらえればと思います。
①一問一答形式で、書かないで頭の中で解いていく(答えていく)
②今度はちゃんと書いて、解いていく
という順番でやってみてください。
苦手意識をなくす方法は、ひとつは点数を取ることですね。
平均点取れれば苦手とは言わないと思うので、上記の方法でまずは平均点(60点ぐらい)を目指しましょう。
点数が取れる経験をするまでは、正直取り組むのが億劫に感じると思います。でもそこは踏ん張りどころです。
1回点数が取れてしまえば苦手意識もなくなり、避けることもなくなると思います。
がんばってくださいね!!!
中3の受験生です。毎回英語のテストで40点以上しか取れません。英語の勉強方法を教えて下さい。
アップルパさん
こんにちは、山田優輔です。
コメントいただきありがとうございます。
英語の勉強法は「中学生の英語勉強法」で解説しているので、参考にしてください。
40点ということは、英単語の知識も不足していると思うので、英単語の勉強法については「中学生の英単語の覚え方」を参考に、毎日英単語の勉強をするようにしてください。
英単語と並行して、文法の勉強もした方が良いです(長文はひとまずやらなくてOKです)。
中3生ということで受験も近いと思うので、受験対策向けの問題集を1冊買って取り組むのが良いと思います。
問題集についてもおすすめのものを紹介しているので、こちらもぜひ参考にしてください!
⇒「高校受験英語で9割取るためのレベル別おすすめ問題集27選」
3つの硬貨を同時に投げるとき、少なくとも一枚は裏が出る確率。