- 「国語がどうしても苦手で…」
- 「国語はどう勉強すればいいかわからない…」
あなたも上記のように国語の勉強法がわからず途方に暮れているかもしれません。
学習塾を経営していると「国語」に関する悩みや相談はたくさんいただきます。
でも安心してください。
国語の定期テストの勉強法はあります!
点数の取り方があります!
この記事では国語の勉強方法をステップ別に、具体的なやり方を詳しく解説していきます。
この記事に書いてある勉強法を実践していけば、あなたの国語の悩みはすっきり解消されるはずです。
それでは見ていきましょう!
まずは国語のテストのことを知る
まずはなぜ国語のテストで点を取ることができていないのか?
テストで高得点を取るためには何の勉強が必要なのか?ということを解説していきます。
国語のテストはこの問題が出題される
国語のテストの問題は、主に次の3つに分けられます。
1つずつ見ていきましょう。
- 漢字
定期テストでも高校入試でも、漢字の配点は読み書き合わせて20点前後〜30点あり、かなり大きなウエイトを占めています。
- 文法
基本的に10点前後ほど出題されます。テストの回によっては読解問題が減り、文法の配点が多くなることもあると思います。文法問題は次の種類があります。
- 品詞
- 活用形・活用の種類
- 敬語・敬語の種類
- 読解問題
残りの60〜70点分が読解問題になります。テスト範囲によってはここが古文になったりします。「“国語”が苦手で…」と言う方がイメージしている“国語”はこの読解問題のことだと思います。読解問題は「選択問題」「書き抜き問題」「記述問題」があり、次の種類があります。
- 接続詞を答える問題
- 指示語(「これ」「それ」など)を答える問題
- 「〜はなぜか?」と理由を問う問題
- 筆者の主張を問う問題
国語の問題はこれらの問題が出題されます。
前回のテストの答案用紙を引っ張り出して、まずは自分がどこができていないのかを認識してください。
何が足りないのかをわかっていないと遠回りになってしまいますから。
それでは、次からステップに分けてひとつひとつの攻略方法を解説していきます。
【ステップ1】漢字の攻略方法
まずは漢字の勉強をしてください。
配点が大きい上に、一番手っ取り早く点数を上げられるからです。
漢字は何が出題されるかわかっている
漢字は簡単に満点を取ることができます。
なぜなら、指定されたテスト範囲の「国語or漢字のワーク」「教科書」からそのまま出るからです。
だから、出題される漢字はすべてわかります。
ここで満点を取らないのは大損です。
前回のテストで半分ほどしか取れていない人は、漢字だけで10点は上がります。
必ずすべて覚えてからテストに臨んでください。
漢字の上手な覚え方
漢字を効率良く覚えるにはコツがあります。
細かい手順については「二度と苦労しない漢字の覚え方」で解説しているのでチェックしてください。
漢字・英単語・理科・社会などの暗記ものでとにかく大事なことは「頻度を多くする」ことです。
何かを覚えるときは、とにかく書きまくっても覚えられません。
また、「一気に15回練習」よりも「3回練習を時間をあけて5回」の方が非常に効果的です。
人の脳は、接触頻度が多いものを「重要なこと」と認識し、記憶に定着するからです。
漢字の覚え方の具体的な手順の概要だけお伝えすると、次の通りです。
漢字を覚えられたら、読解問題の勉強をします。
【ステップ2】読解問題の攻略方法
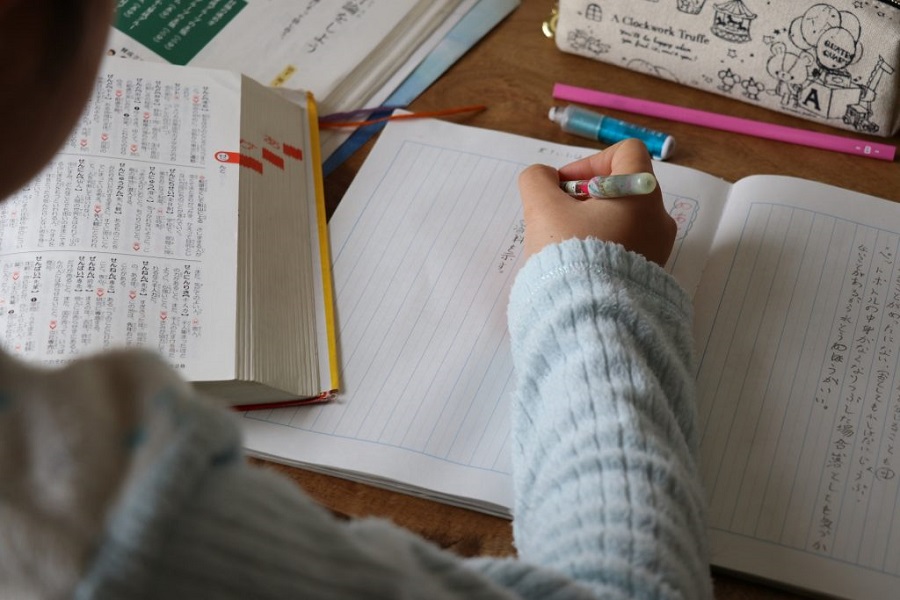
国語のテストで最も配点が大きいのがこの読解問題です。
また、国語が苦手な人の多くが悩んでいるのもこの読解問題でしょう。
読解問題の点数の取り方を解説していきます。
読解問題は“ココ”から出題される
定期テスト〝だけ〟なら読解力はほぼ必要ありません。
なぜなら、定期テストの読解問題は、授業でやった教科書の本文であり、出題される文章も、出題される設問・設問箇所がすべてネタバレされているからです。
というのも、学校の授業で本文は全て解説されます。
その”解説された部分”が問題になるところです!
それで、その解説はノート(プリント)に全て書いてあるわけです。
授業のノート(プリント)をマスターする
つまり、ノートで解説された部分を理解して覚えるだけでかなり点数がアップするはずです。
どこを勉強すればいいのかも明確ですし、覚えておくこともそれほど多くはないので、確実に覚えてください。
具体的に例をあげると、学校の授業では次のような解説をしてくれているはずです。
そして定期テストでは、次のように問題を出してきます。
小説文も同様です。
といった具合です。
古文の場合は、「現代仮名遣い」「単語の意味」「主語は誰か」の3つです。
古文は主語が省略されています。
だから、初めて見る僕らは話が全く見えてきません。
でも授業で、
- 「ここはこの主語が省略されています」
- 「この単語は〜という意味です」
と解説し、全文訳もしてくれます。
そしてテストで
- 【問】傍線部の主語は誰か答えなさい。
- 【問】傍線部の意味を答えなさい。
と出題されます。
この授業で解説された部分を覚えれば得点できるので、そういう意味では定期テストの国語は「理科・社会」と同様、暗記の教科です。
学校ワークをマスターする
ノートに加えて、学校ワークも同じようにマスターすれば完璧に抜けが無くなります。
ワークの上手な取り組み方は「プロが教える中学生の点数爆上げ勉強法!3か月で100点アップの具体的手順」で解説しているので確認してください。
学校ワークがない場合の対処法
学校ワークがない場合は、市販の教科書準拠ワークで演習を行いましょう。
「国語のワークは配られていない」という学校も結構あるようです。
この教科書ワークで勉強すれば出題される問題のイメージなどもできるので、ぜひ取り組んでください。
東京書籍:新しい国語
三省堂:現代の国語
教育出版:伝え合う言葉 中学国語
光村図書:中学校 国語
入試や模試でも通用する読解問題の勉強方法
ここまで解説した読解問題の勉強方法は“定期テスト用”の勉強方法です。
実際の模試や入試では出題される問題がわからないので、今回の勉強方法はできません。
模試や入試での読解問題の勉強方法やコツは別の記事で解説します。
【ステップ3】文法問題の攻略方法
最後に文法問題です。なぜ最後なのかというと、文法は配点が低いですし、覚える量も非常に少ないです。
だから、テスト前2、3日毎日1周ずつやれば十分覚えられると思います。
文法のワーク・プリントをマスターする
文法は学校ワークの文法ページや、配布されたプリントをとことんやりましょう。
ワークやプリントからそのまま、あるいは数学の計算問題のように、ことばが少し変わっただけの問題が出題されます。
ワークの取り組み方はその他の教科と同じです。
どうしても文法がわからない場合の対処法
「学校のワークや教科書を見てもイマイチわからない…」という場合は、市販の参考書を買ってみてください。
どれも基本的に見やすくわかりやすいです。
「ひとつひとつわかりやすく」シリーズ
この参考書はイラストも多いので、活字が苦手な人向けです。
また、無料解説動画も付いているので無理なく国語の超基礎から学ぶことができます。
これでわかる中学国文法
問題の校正が「必修問題」→「チェックテスト」と段階的にレベルアップしているので、スモールステップで学習することができます。
また、テストでよく出題される識別問題について、巻末に「語の識別」としてまとめられているのが良い点です。
しっかりと文法の勉強や復習をしたい人向けには一番おすすめの参考書です。
くもんの基礎がため100%中学国語
問題が豊富に載っているため、どんどん問題をこなしたいはこの参考書がおすすめです。
国語のテスト勉強方法まとめ
国語の定期テストで高得点を取るためには、「普段の授業」を大切にしてください。
- きちんと授業を聞く
- 授業で聞いたことをきちんとノートに書く
これが最善の勉強方法です。
その上で
- 漢字をマスターする
- 読解問題はノートをマスターする
- ノートの内容を攻略したら学校ワークをマスターする
- 文法問題をマスターする
をしていってください。
「国語の勉強方法がわからない」という人もこの記事の内容通りに勉強を進めていってください。
国語はむしろ勉強しやすく、簡単に点数を上げられる教科です。
次回のテストで点数アップ間違いなし!!!

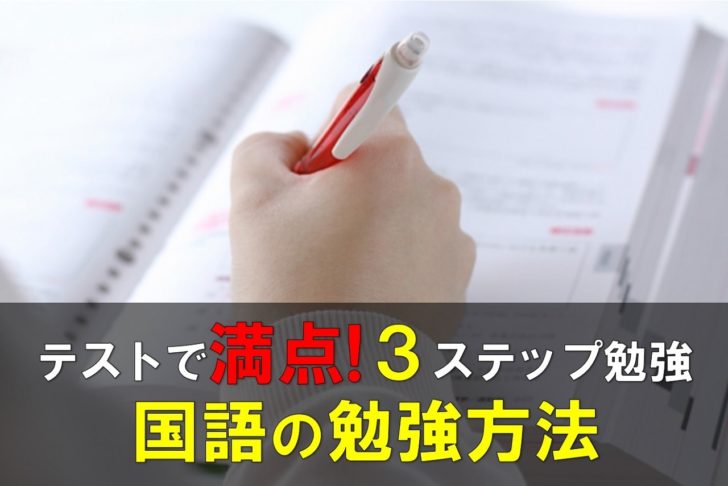
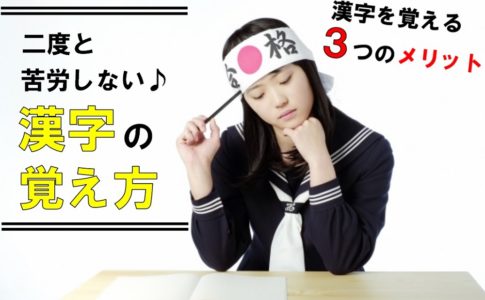
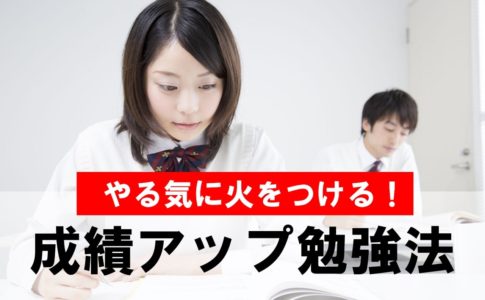
















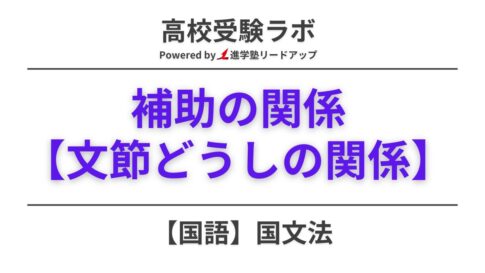
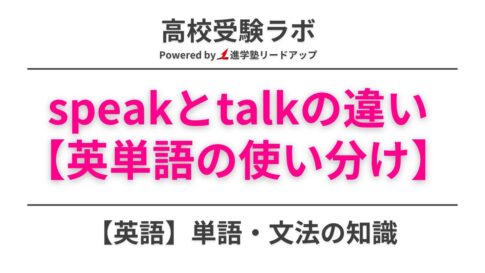











こんにちは!
高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
進学塾リードアップのHPはこちら