補助の関係では、特に「補助動詞」や「補助形容詞」がよく使われます。
このように、補助の関係を理解して使いこなせるようになると、文章を読むときにも、書くときにも、とても役に立ちます。
これらのように、補助語があると、ただ単に「読む」「食べる」「やる」だけでなく、その行為に込められた気持ちや状況まで伝えることができます。
このような補助の関係をしっかり理解することで、文章の意味がより深く読み取れるようになりますし、作文や読解の力もアップします!
文節どうしの関係の見分け方【実践編】
実際の定期テストでは、補助の関係は「2つの文節の関係を答えなさい」というかたちで出題されます。
文節どうしの関係には、次のようなものがあります。
修飾の関係
修飾の関係は、主語や動詞などに対して説明を加えるのが役割で、内容を詳しくするためのものです。
例えば、「速く走る」の「速く」は、どのように走るかという情報をくわしく説明している「修飾語」です。
「補助の関係」と「修飾の関係」の違い
補助の関係は“意味を足す”ことであり、修飾の関係は“詳しく説明する”ことです。
たとえば、「見てしまう」の「しまう」は、動作が完了したことや、思わずやってしまったという気持ちを表す補助動詞ですが、「じっと見る」の「じっと」は、“どうやって見るか”を説明している修飾語です。
このように、似ているようで実は目的が違うのが、補助と修飾の大きなポイントです。
並立の関係
たとえば「食べて、寝る」のような表現では、「食べる」も「寝る」もどちらも主な動作として並んでおり、同じ重さを持っています。
このように、2つ以上の動作が独立してつながっている関係を「並立の関係」と言います。
「並立の関係」では、動作Aと動作Bがそれぞれ自立しており、動作が2つとも主役、「〜て」の形で順番に並んでいるだけです。
補助の関係
前の動作に後の語が意味を補う形でくっついているものを「補助の関係」と言います。
たとえば、「走ってみる」の「みる」は、動作に“試してみる”という意味を追加する補助動詞で、走るという行動に新しい意味やニュアンスを加える役割を果たします。
「食べてしまう」のような表現では、「食べる」が主な動作で、「しまう」はその動作に気持ちや状況を加えるために使われています。
補助の関係では、「食べる」が主役であり、「しまう」はその意味を広げたり深めたりする“サポート役”として働いています。
補助の関係では、ある動詞や形容詞に別の言葉がついて、意味を補ったり助けたりするのが特徴です。

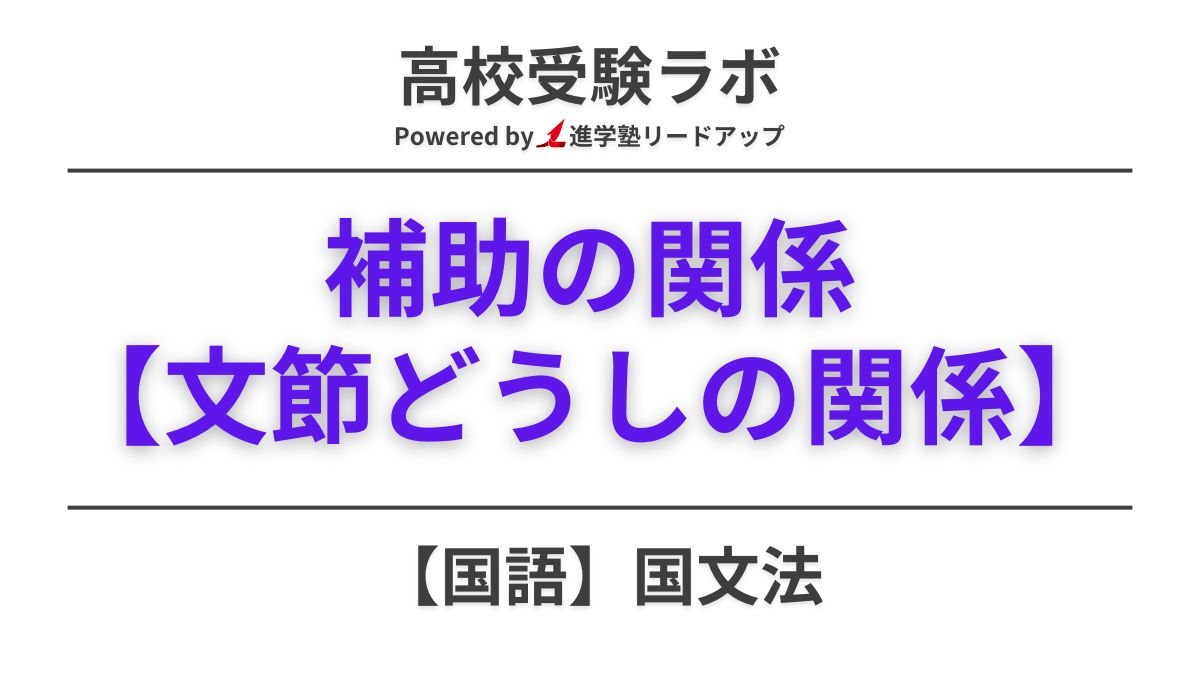
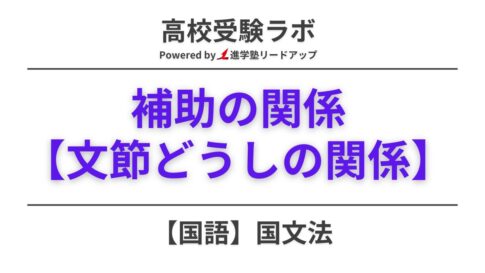
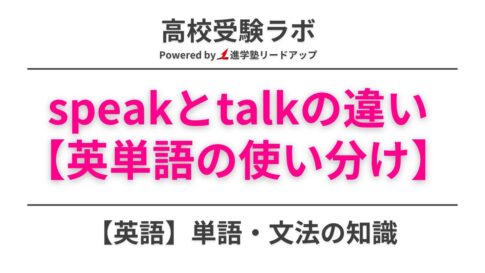











「〜てみる」「〜てしまう」「〜ておく」など、主な言葉(たとえば動詞)に他の言葉がくっついて、その意味を助けたり補ったりするものを「補助の関係」といいます。